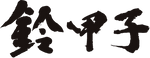櫛引八幡宮と「国宝模写」の原点を辿る -赤糸威大鎧(菊一文字の鎧兜)と鈴甲子の技術-
はじめに
青森県八戸市に鎮座する櫛引八幡宮(くしひきはちまんぐう)は、800年以上の歴史を持ち、青森・岩手一帯を統治した豪族・南部氏の総鎮守として知られており、国宝甲冑2領を含む古来の名品を所蔵しています。
そのうち1領の「国宝 赤糸威大鎧(菊一文字の鎧兜)」は、装飾金具の豪華さなどから、奈良県の春日大社で所蔵されている「国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾)」と共に、「国宝大鎧の双璧」と称されています。
そして2025年7-9月に開催の企画展「究極の国宝 大鎧展」に、これら双璧が史上初めて並列展示されることになり、大きな話題となっております。
甲冑工房である鈴甲子は、櫛引八幡宮に所蔵されている国宝甲冑を模写したミニチュアサイズの五月人形を製造・販売しており、20年以上にわたり良いご縁をいただいております。
そこで今回は、櫛引八幡宮でその守護や公開を担う 營田 稻太郎(つくた とうたろう)宮司に、当時を振り返ってのお話、そして今回の企画展に向けた想いをお聞きしました。
 写真奧:櫛引八幡宮の營田稻太郎宮司
写真奧:櫛引八幡宮の營田稻太郎宮司
写真手前:鈴木雄一朗(鈴甲子)
1.「国宝の価値を伝える」取り組みと鈴甲子との歩み
・お付き合いのきっかけとしては、20年ほど前に我々の方から突如「国宝の模写をしたいので調査をさせてほしい」とご相談させていただいたと聞いています。その時はどのような印象を持たれましたか?
はい。率直に申しますと唐突なお話だと思いましたが、当時実は私も宮司に就任して間もない頃でして、右も左もわからなかったため、「まずはお話を聞いてみよう」と対応を行ったことを覚えています。
・実際に話を聞いてみていかがでしたか?
当宮では、国宝を守るという観点から「所蔵する国宝は貸し出さない」「展示しても近距離では見せない」という思想が強く根付いていました。そのため、なかなか内部でも合意を取るのは難しいところもあったのですが、私個人の意見としてはこのままでは国宝の価値や意味が後世に伝わらないのでは、という懸念を抱いておりました。
そのため、こうして飛び込みでお願いをしにきてくださった工房の鈴甲子さんの想いを無下にするはできないと思い、周囲を説得し了承することとしました。
ただ、私としても「国宝の価値を後世につなげる」ことを願っているため、「本気でこだわって再現するのなら…」と条件をつけた上で、思い切って実物を間近で調査する機会を差し上げたのが、鈴甲子さんとのお付き合いの始まりです。

写真は左から營田宮司と鈴甲子雄山(奥三代目,右四代目)
・模写製作の中で印象的だったことはありますか?
製作を進める中で、再現度を高めるために何度も確認や意見を求められたことをよく覚えています。
大鎧としての機能や、意匠としての「菊一文字」を丁寧に掘り起こし、咀嚼-そしゃく-して形にしていくヒアリングや、デザインをできるだけ忠実に模写したいという根気に熱意を感じました。
「しっかり再現したものを作りたい」という鈴甲子さんの姿勢に私たちも、本物を見せる意義を感じることができました。
こうしたやり取りを経て完成した作品を、平成15年に神社へとご奉納いただきました。
 国宝模写 菊一文字赤糸威大鎧 2/5スケール (大鎧展で展示中)
国宝模写 菊一文字赤糸威大鎧 2/5スケール (大鎧展で展示中)
2.国宝との距離を縮めた、新たな展示の試み
・その後、国宝の価値や意味を伝えるためにどんなことに取り組まれたのでしょう?
鈴甲子さんとのやりとりを経てから、国宝を後世へと言う想いがさらに強くなりました。
そのため国宝をただ保管するのではなく、「見て感じてもらう」ことに重点を置いて、古くからある国宝館を新調するために動き始めました。
それまでの国宝館では、展示台の上に鎧を収納するためのお櫃をのせ、そのさらに上に鎧を乗せていたため、細部までよく見ることができないレイアウトになっていました。
また、壁沿いのショーケースのような横長の展示スペースのため、後ろまで見ることができなかったのです。
そのため新調において最もこだわったのは、細部まで自分の目で見ることができる展示構造でした。独立した空間で前後左右どこからでも鎧が見れる構造とし、目線の高さに合わせて台座を設計することによって、じっくりご覧になりたい方には見やすい展示になったと思います。
また、いつでも見ることができるようにという部分にもこだわりがあります。通常、劣化からの保護の観点から、収蔵庫と展示スペースを分けて、一年に何度か見せる形が一般的ですが、青森にわざわざ見にきてくださった方々が「見ることができなかった」と言う残念な思いを残さないようにしたいと考えておりました。文化庁でもそれまでの保存重視の収蔵庫から展示機能付きの収蔵庫の建設への建設要項が変更となりましたので、展示機能を備えた国宝の収蔵庫を日本で初めて設計しました。
これは通常の収蔵庫とは異なり、展示スペース自体が収蔵庫としても機能をしているため、いつでも所蔵品を観覧できることが大きな特徴です。
移動による劣化を防ぎつつ、来館者に古代の人々の繊細かつ豪快な手仕事を間近に感じられる空間になっております。
建設費は一般的な展示施設よりも大きく膨らみましたが、多くの方々の支援を賜り完成しました。御社もこの建設プロジェクトに賛同して下さいました。その節はありがとうございました。
3. 八戸に眠る国宝を知る、企画展がつなぐ新たな縁
・今回の春日大社の企画展「究極の国宝 大鎧展」では、来場者にどのようなことを伝えたいですか?
今回の企画展は、私がずっと大切にしてきた「国宝の価値や意味を見て感じてもらう」というテーマに直結するものです。多くの方に櫛引八幡宮の国宝を見ていただけること自体が、大きな意義だと思います。
「東北にこれほどの甲冑がある」というのは、現代人にとっても驚きの事実でしょう。今回の展示をきっかけに、八戸に眠る国宝の存在を知っていただき、もう一つの国宝(白糸威褄取鎧-しろいとおどしつまどりよろい-)にも興味を持ってもらえたら嬉しいですね。

国宝模写 白糸褄取大鎧 2/5スケール (大鎧展で展示中)
・入口付近に、弊社が奉納した菊一文字鎧と白糸褄取鎧が展示されていますね。
私たちと共に練り上げた御社の作品を国宝と並べて展示することで、来場者にとって国宝がより身近な存在となり、その価値を次の世代に受け継いでいく一助になればと考え、春日大社様にご提案させていただき、実現しました。
現代の人たちで力を合わせて国宝に近づこうとした作品を、国宝と合わせてご高覧いただけると幸いです。
 国宝殿1階スペースにて撮影
国宝殿1階スペースにて撮影
インタビューにご協力いただき、誠にありがとうございました
まとめ
櫛引八幡宮様とは、20年ほど前より模写製作のための機会とご指導をいただいたことで、交流が始まりました。
鈴甲子が “時代背景を伴う忠実な模写作品を作る五月人形の工房” として評価されるようになったのは、宮司の營田(つくた)さんのような、実物を所蔵する立場の方から、歴史や造形に関する深いご理解とご協力をいただけたからに他なりません。
もし營田さんが、「国宝は見せない・貸さない」というスタンスであれば、今回のような展覧会は開催されず、竹虎雀の鎧との『夢の共演』のような展示も実現されなかったのではないでしょうか。

今回は、鈴甲子の国宝模写の原点を知ることができ、改めて貴重な展示会に立ち会えていることを実感しました。
日本古来の文化である「節句」の中の、五月人形製作を担う鈴甲子の作品を、今回の企画展と合わせてご覧いただけると幸いです。
▽▼春日大社「究極の国宝殿」ホームページ▼▽
究極の国宝 大鎧展 - 日本の工芸技術の粋を集めた甲冑の美の世界
▽▼櫛引八幡宮 国宝館 ホームページ▼▽
国宝館 | 櫛引八幡宮(くしひきはちまんぐう)| 青森県八戸市にある神社