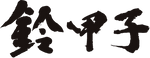春日大社が語る「国宝」の価値 -国宝赤糸威大鎧(竹虎雀飾付)と鈴甲子の技術-
はじめに
五月人形を探している際、工房や職人の紹介で「国宝」という言葉を見かけることがあります。
「でも、国宝って何が特別なの?」と思う方も多いのではないでしょうか。
最近では、人間国宝の凄みを伝える映画『国宝』が上映され、大変な人気を博しており、これまでの日本が培ってきた素晴らしい文化に焦点が当てられています。
今回は甲冑の「国宝」に焦点を当てて、その凄みをお伝えします。
国宝に指定される文化財は、日本の歴史や美意識、そして最高峰の職人技が凝縮された“究極の作品”です。
五月人形の甲冑製作を行う鈴甲子はこれまで数多くの国宝を模写し、日本の国宝の素晴らしさを五月人形として現代の人々に伝える取り組みを行なってきました。
その「国宝」の魅力を、2025年7-9月に「究極の国宝 大鎧展」と題して数々の国宝の展示企画の運営を担う、春日大社の荒井 権禰宜(ごんねぎ)に語っていただきました。
 写真奧:荒井 清志(春日大社 権禰宜/学芸員)さん
写真奧:荒井 清志(春日大社 権禰宜/学芸員)さん
神職としての活動と合わせ、春日大社に伝わる国宝をはじめとする貴重な文化財の保護・管理を担当。甲冑や刀剣を中心とした展覧会の企画運営にも携わる。
写真手前:鈴木 雄一朗(甲冑工房「鈴甲子」)
1. 国宝展の概要と意義
・2025年7月から開催される「究極の国宝 大鎧展」。鎧好きには大きな話題になっていますが、概要を教えていただけますか?
今回の企画展は、国内を代表する大鎧を一堂に集めた大規模な展示です。
国宝指定の甲冑類18点中、半数の9点が展示され、重要文化財や普段は目にできない貴重な作品もご覧いただけます。
国宝というと「古いもの」という印象を持たれる方も多いですが、実際にはその時代の日本が誇る、最高の工芸技術を結集させた到達点として認められたものです。
そのため、保存や展示も厳格に管理され、簡単には人目に触れられない貴重な存在になっております。

2. 竹虎雀という特別な甲冑
・中でも目玉とされる国宝「赤糸威大鎧(竹虎雀飾付)」、通称「竹虎雀」。どのような点が特別なのでしょうか?
一番の特徴は、その豪華さです。
装飾金具を付けられるところすべてに施したほどで、定型を超えて限界まで飾り立てた、ある意味「ぶっ飛んだ」作品とも言えます。最高の甲冑を作るため、当時の職人たちが全ての技術を総動員した、その姿勢自体が日本的で感銘を受けます。

〈参考〉鈴甲子の工房で使用している竹虎雀の金具
・金具の素晴らしさ以外には、どんな魅力があるのでしょうか?
竹虎雀には、合理的に考えれば必要のない装飾や技法が多くあります。
わかりやすいものでいうと、「伏せ縫い(ふせぬい)」と呼ばれる革の縫製技術です。鹿の革同士をつなげることが目的なのですが、わざわざ多色の色を使いデザインするように縫われています。

〈参考〉鈴甲子による伏せ縫いの再現
また帯紐も「両面亀甲(りょうめんきっこう)」という、表裏どちらにも亀甲柄が出る、現代技術での再現ができていない組み方の帯を使っていたりします。
これらは大将を守るだけでなく、讃える存在として美しさを極めるためのものです。
「大将を象徴するものとしてふさわしいものを」という手間を惜しまない感性に、日本の美意識の原点を感じます。
3. 企画展の記念作品・竹虎雀の模写制作について
・今回の企画展の記念作品として、国宝「竹虎雀」の三分の一サイズの模写制作を鈴甲子にご依頼いただきました。その経緯を教えてください。
最初から決めていたわけではありません。企画展に向け国宝の甲冑を持つ青森県の櫛引八幡宮さんを訪れた際に、偶然鈴甲子さんの作品を目にし、「いいものを作っている」と感じたのがきっかけです。
国宝の模写には、当時の金具を小さく精巧に再現する技術や、時代考証を踏まえた形で大鎧としての意味を損なわずに仕上げる力が必要です。鈴甲子さんはその両立ができている工房だと感じました。
・どんなところでそう感じていただけたのでしょうか?
通常だと省きがちな細かい部分にこだわりをみました。
竹虎雀は「大鎧」という形式に分類されますが、馬に乗った状態で戦うことを想定されて作られた甲冑になります。そのため、様々な隠れた機能が盛り込まれています。そうした機能まで再現されているところが素晴らしいと思いました。
・例えば、どんな機能でしょうか?
わかりやすい例で言うと、「逆板(さかいた)」や「矢摺の革(やずりのかわ)」がきちんと表現されているところです。
 〈参考〉鈴甲子の模写作品による逆板の再現
〈参考〉鈴甲子の模写作品による逆板の再現
逆板は前傾姿勢をとったときに突っ張らずに前屈みになれるという機能を持っています。また馬に乗った際の上下動を吸収して肩当てがずれないようにする役割も担っており、騎射戦が主流だった大鎧の時代としての大きな特徴になります。
また矢摺(やずり)の革も箙(えびら)という右の腰に取り付けた矢筒から矢を抜き出す際に、矢が引っかからないよう、右肩の大袖の裏にだけ革をつけたとされる機能です。
 〈参考〉鈴甲子の模写作品による矢摺の革の再現
〈参考〉鈴甲子の模写作品による矢摺の革の再現
4. 記念作品の持つ意味
・今回の企画展の記念作品として制作した「国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾付) 三分の一」には、どのような想いを込めていらっしゃるのでしょうか?
この記念作品は、単なるお土産やレプリカではありません。
**本物の国宝をより多くの方に身近に感じていただき、日本の文化や職人技へのリスペクトを深めてもらうための“架け橋”**として制作をお願いしました。
国宝は本来、厳しい管理のもとに保管され、簡単に手に取ることはできません。
しかし、この記念作品を通じて「国宝が持つ美意識や技術の一端」を感じてもらえれば、日本の職人文化の奥深さや、それを支える人々の努力にも目を向けてもらえるはずです。

・このような取り組みは今後も続けていかれるのでしょうか?
はい。春日大社としても、文化財をただ守るだけでなく、現代の方々が“体験し、理解し、次世代に伝えられる形”で届けていくことが大切だと考えています。
今回の記念作品も、その一歩です。手に取った方には、所有する喜びと同時に、日本の伝統や職人への敬意を感じてもらえたら嬉しいですね。

鈴木:今回はインタビューにご協力いただき、どうもありがとうございました。
荒井:こちらこそ、どうもありがとうございました。
まとめ
国宝は、日本の歴史や文化、そして職人技の集大成として選ばれる特別な存在です。
春日大社の荒井氏はこう締めくくります。
「今回の企画展を通じて、職人文化や美意識を未来に伝えていけることを嬉しく思います。」
その模写を任された工房「鈴甲子」は、時代考証や精緻な技術を備えた、数少ない工房のひとつです。
その技術と姿勢は、五月人形の作品作りにも息づいています。
日本古来の文化である「節句」の中の、五月人形製作を担う鈴甲子の作品を、今回の企画展と合わせてご覧いただけると幸いです。

▽▼春日大社「究極の国宝殿」ホームページ▼▽