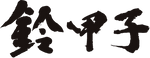1/3武将兜の各パーツの特徴や素材をご紹介
はじめに
こちらの記事では、1/3スケールの戦国武将兜の各パーツの名称や素材について細かくご紹介していきます。
ご紹介する作品は、

・1/3スケール 伊達政宗公兜
・1/3スケール 上杉謙信公兜
の2点です。
兜鉢(かぶとばち)

1/3スケールの伊達兜は、宮城県の仙台市博物館に収蔵されている「黒漆五枚胴具足(くろうるしごまいどうぐそく)」の兜を模写した作品です。
鈴甲子で伊達兜は他のシリーズや他のサイズでも製造しておりますが、実物のシルエットや色合いなどをできるだけ忠実に再現したものが、こちらの兜です。
兜鉢は「六十二間筋兜(ろくじゅうにけんすじかぶと)」というものです。
六十二間筋兜とは、62枚の細長い鉄板を頭の形になるよう重ね合わせて強度を高める工夫が凝らされており、戦国時代に流行した形になります。
鈴甲子では、鋳造(型に金属を流して造形)にて、この兜鉢を表現しています。弊社ショールームでは、等身大の六十二間筋兜を製作・展示しております。

1/3スケールの上杉兜は、山形県の上杉神社に収蔵されている、紫糸威伊予札五枚胴具足(むらさきいとおどしいよざねごまいどうぐそく)の兜を模写した作品です。
兜鉢は頭形兜(ずなりかぶと)といい、読んで字のごとく頭の形に似た兜です。実物は3枚から5枚の鉄板から成形した兜で、こちらも戦国時代に多く作られた兜鉢です。
鈴甲子では、鋳造(型に金属を流して造形)にて、この兜鉢を表現しています。
| 素材 | 合金 |
前立(まえだて)

前立(まえだて)とは、兜の正面に付ける装飾のことです。
兜全体のデザインの中でも非常に目立つ部分で、元は装飾としての意味合いが強かったのですが、徐々に武士の身分や個性を象徴する重要な飾りとなっていきます。
伊達兜は弦月(げんげつ)の前立です。弦月とは三日月のことです。月には神様が宿るという考えから、身を護るために月をモチーフにしたと言われています。
また、月は欠けても満ちることから不滅や再生の象徴とされ、弦月が満月に変化していくことから成長や大きな可能性をイメージさせます。

上杉兜の前立は「日輪(にちりん)弦月」と呼ばれます。前述の三日月に、太陽を表す「日輪」が重なった前立です。
太陽もまた、天照大御神(あまてらすおおみかみ)など、太陽神の伝説が数多く残っています。月と太陽の両方が付いたこちらの前立は、信仰心の強い武将として知られる、上杉謙信公らしい前立です。
| 素材 | 真鍮に24K鍍金 |
錣(しころ)
錣(しころ)とは、兜(かぶと)の後ろや側面に付いている部分で、首や肩を保護するための重要なパーツです。兜の頭部だけでなく、首元から肩のあたりまでをカバーすることで、敵の攻撃や矢から武将の体を守る役割を果たしていました。
穴の空いた板(小札‐こざね‐)に、糸を通す威(おどし)という技法を使っており、糸の色や模様によって兜の印象が作られていきます。

伊達兜は艶を抑えた黒の小札を、紺色と黄色の糸で編んでおり、

上杉兜は手触りの良い牛革で出来た小札を、紫色の糸で編んでおります。
| 素材 | アルミまたは牛革、正絹糸 |
吹き返し(ふきかえし)

吹き返しは、兜(かぶと)の前部や側面に取り付けられた、外側に折り返したような形をした部分です。
伊達の兜、上杉の兜ともに家紋のデザインです。上杉兜は竹と雀の家紋が入っており、伊達兜は透かし彫りという、向こう側が見える梅紋の吹き返しです。
| 素材 | アルミ |
忍緒(しのびのお)

| 素材 | 人絹 |
付属品について
作家札

鈴甲子雄山の作品である証となる、作家札です。
| 素材 | 天然木 |
袱紗(ふくさ)

布地を表裏二枚合わせ、または一枚物で、ふろしきより小さい方形に作ったものを袱紗(ふくさ)と言います。
進物に掛けたり、茶道で茶碗を受けたりするためにも使われており、礼儀を尽くす際に用いられています。
通常の1/3スケールの戦国武将兜は、黒の袱紗が付属します。
| 素材 | 人絹 |
芯木(しんぎ)

| 素材 | 天然木 |
お櫃(おひつ)

戦国武将の兜には、収納のためのお櫃(ひつ)が標準でついております。
お櫃は、兜やその他の飾り物を安全に収納するための箱です。使用しないときは、しっかりと収納することで、埃や汚れから守ることができます。これにより、飾り物の劣化を防ぎ、長持ちさせることができます。
また、防湿の観点からもお櫃は足で箱を持ち上げている構造のため、湿気を下に逃す構造になっています。
金属や絹糸は多湿の環境における劣化が早いので、お櫃で収納することをおすすめしております。
戦国武将の兜には、芯木と同じく天然木を黒で塗装し 木の手触りや木目の良さを残したお櫃が付いてきます。
| 素材 | 天然木 |